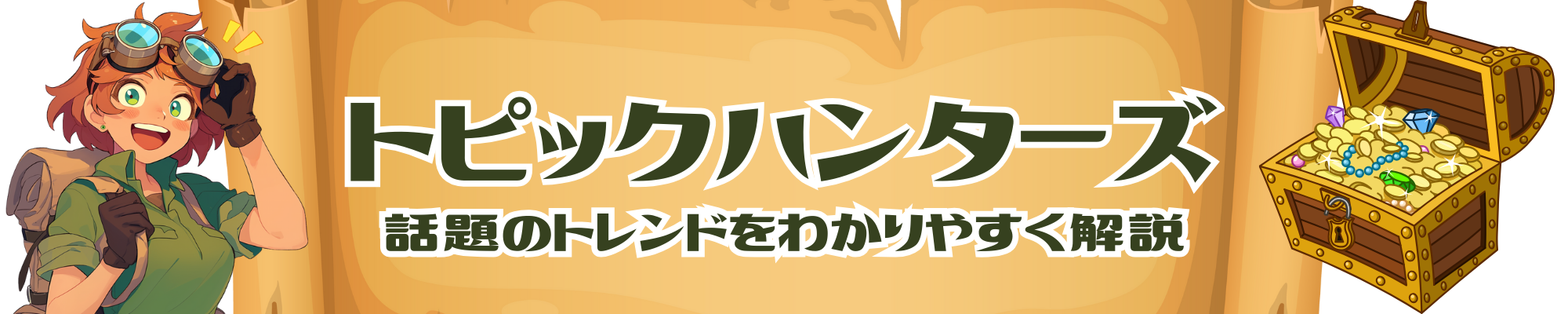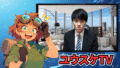はじめに
ソニーと聞けば、誰もが「PlayStation」や「ウォークマン」など革新的な製品を思い浮かべるでしょう。しかし、華やかな成功の裏には、経営危機からの壮絶な“逆転劇”が隠されています。本記事では、ソニーをV字回復へと導いた平井一夫(ひらいかずお)氏のリーダーシップに焦点を当て、書籍『ソニー再生 変革を成し遂げた「異端のリーダーシップ」』を分かりやすく解説します。
・なぜPlayStationは米国市場で世界的大ヒットを記録できたのか?
・高額なPS3発売で生じた大赤字を、どのようにして克服したのか?
・長年の赤字体質だったテレビ事業は、どんな戦略で息を吹き返したのか?
3度の事業再生とは?
バラバラだったSCEAをまとめた平井一夫の覚悟
平井さんは1995年にソニーミュージックからSCEA(ソニー・コンピュータエンタテインメント・アメリカ)に赴任しました。当時、SCEAは指揮命令系統がバラバラで、ヒット商品の「PlayStation」が存在するにも関わらず、社員はストレスを抱えて働いていました。若くして35歳で赴任した平井さんは着任後すぐ「社員との対話」を開始し、1対1で社員一人ひとりと話をし、問題点を抽出して組織の立て直しに着手します。
さらに「つらい仕事こそリーダーがやる」という信念のもと、自ら厳しい人事決断を引き受けて率先垂範し、痛みの伴う組織改革を進めていきます。こうした姿勢が、まさに平井さんのリーダーシップの本質を示しています。
その結果、1998年にはSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント)の決算はゲーム部門で1,365億円を営業利益として叩き出しました。当然ながらSCEAの貢献も大きい結果となりました。
売れたら赤字?PlayStation 3の大ピンチを脱却
2006年、PS3は「家庭用スーパーコンピュータ」として極めて高性能に設計されましたが、発売前に約6万2790円という高価格が発表されて「高すぎる!」と世間から大批判を受けます。発売時に約4万9980円に下げたものの、1台売るたびに赤字という状況でした。結果、2006年度にはSCEAで約2300億円の赤字を計上。社内からは「ソニーを潰す気か!」と非難が飛びました。
この危機でプレイステーションの父・久夛良木(くたらぎ けん)氏が退任し、2006年12月に平井さんがSCEI(ソニー・コンピュータエンタテインメント本社)社長に就任します。平井さんは社員に「PlayStation 3はゲーム機だ」と訴え、価格を下げるために徹底したコスト削減を進めました。
その結果、2009年9月にはPS3を2万9980円まで値下げできる目処が立ち、発売から3年半の時を経て利益を出せる状態にすることができました。
痛みを伴う改革の末、テレビ事業再建
ソニーのテレビ事業「ブラビア(BRAVIA)」は海外勢との価格競争に敗れ、10年連続で赤字となっていました。平井さんは痛みを伴う改革を実施します。2014年にテレビ部門は分社化し、量から質に事業戦略を変更しました。
またパソコン事業「バイオ(VAIO)」は収益化が困難と判断し、5000人の人員削減と事業売却を決断します。「エレクトロニクスを知らない」「”外”の人間だから冷徹な判断が下せる」など平井さんは厳しい批判に心を痛めました。
痛みを伴う事業改革の結果、2003年から2013年まで続く赤字を2014年で黒字化することができました。
書籍の感想
3度の事業再生に込められた覚悟
事業を再生するということは、何かを選ぶ代わりに、何かを切り捨てなければならないという厳しい選択でもあります。すべてを守ることはできない――そんな現実と向き合いながら、ソニーという巨大企業のかじ取りをしてきたのが平井さんです。
一見、ソニーの社長というと雲の上のような存在に感じますが、本書を読んで感じたのは、平井さんもまた悩み、葛藤しながら決断を重ねてきた一人の人間だということ。そこに、私たちと同じような「等身大の苦悩」が確かにありました。
平井さんの経歴と人間性に触れて
平井さんはお父さまの転勤により、小学1年生のときにニューヨークへ引っ越されました。「帰国子女」と聞くと華やかなイメージがありますが、実際には現地で差別を受け、強い孤独感や無力感を味わったそうです。
さらに、小学4年生で再び日本に戻ったときには、逆に日本の文化にカルチャーショックを受けたとのこと。こうした多様な環境で育った経験が、平井さんにとって「異なる意見=異見」に耳を傾ける力を育んだのではないかと感じました。どんな立場の人とも対話を大切にする姿勢は、幼少期の体験に根ざしているのかもしれません。
久夛良木さんのカリスマ性に学ぶ
「プレイステーションの父」として知られる久夛良木健さんは、まさにカリスマ的な存在です。研究者としての探究心、プロダクトプランナーとしての先見性、経営者としての判断力、マーケッターとしての視点、そしてクリエイターとしての情熱──そのすべてを高いレベルで発揮し、こだわり抜いた仕事ぶりが印象的です。
平井さんは、そんな久夛良木さんを「鬼才」と表現しています。革新的なサービスを生み出すには、ひとつの肩書きにとどまらない幅広い視点とスキルに合わせて、熱すぎる情熱が必要だということを感じました。
まとめ「決断と覚悟の先にある“再生”」
『ソニー再生』を通して感じたのは、経営者・平井一夫さんの「人としての強さ」でした。順風満帆に見えるソニーにも、プレイステーション、テレビ事業、PC事業など、いくつもの危機がありました。そのたびに平井さんは逃げずに向き合い、痛みを伴う決断を重ねてきました。
「つらい仕事こそリーダーがやる」「異なる意見にこそ耳を傾ける」という姿勢は、会社経営に限らず、私たちの日々の選択や人間関係にも通じる考え方だと思います。
本書は、ビジネス書でありながらも、一人の人間がいかにして“再生”を導いたのかを描いた、まさに等身大のドラマです。仕事に悩んでいる人、これからリーダーを目指す人に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。